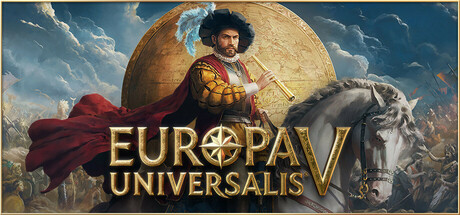今日は軍事・外交・研究をまとめて“事故らない順序”に並べ直す回。戦争は準備8割、外交は未然に事故を消す道具、研究は中長期の地力アップ。なお、この連載は公式チュートリアルの内容と流れを土台に、要点をあたし流の言い換え&“つまずき対策”で補強してるよ。
開戦の順序と外交の土台
1) 開戦前チェックリスト(Unpause前にここだけは)
- 戦争目標(何を取る?何を守る?):1〜2個に絞る。欲張りは長期化の元。
- 軍維持スライダーを戻す:戦闘の数か月前から上げて士気を満タンに。
- 将軍の配属:主力に1人、包囲・追撃に1人。能力が噛み合う部隊に付ける。
- 補給と兵站:前線まで道路/港/補給線が繋がるか確認。山岳・冬季は消耗に注意。
- 要塞(Fort)と前線:敵が踏み込みにくい位置に要塞ON。逆に背後の要塞は平時OFFで維持費を節約。
- 予備兵力:主攻・支援・予備の最低3枠イメージ。1スタック全ツッパは事故率高め。
2) 外交の基本3点
- 関係改善(Improve Relations):周辺国・潜在同盟候補・大国に常時回す。敵の敵も狙い目。
- 同盟網(Alliances):距離+共通の敵+信頼で固める。序盤は“盾”1〜2枚を確保。
- 抑止(Deterrence):軍事力スコア、要塞線、強い同盟。「殴っても割に合わない」状況を作るのが目的。
3) 研究(技術)の土台づくり
- 優先は課題ベース:いま困ってるのは何?食料・統制・収入・軍の質…。課題に直撃する技術を先に。
- 時代(Ages)との連動:開放される制度は早取りが有利。効果が国全体に波及しやすいからね。
作戦テンプレと外交の応用、研究ロードマップ
A. 作戦テンプレ(最初の6か月)
- 主攻の突破:平野・橋頭堡・補給の良い州を狙う。2:1の局地優勢で確実に勝つ。
- 要塞包囲:砲(包囲力)を最小限連れて、補給線を守りながら静かに落とす。
- 予備は反応用:敵の増援に合わせて側面/退路をカット。勝てる戦闘だけ受ける。
- 戦争スコアの現実主義:目標を取ったら早めの講和。長居は消耗と借金を呼ぶ。
B. 外交の応用
- 勢力均衡(Balance of Power):強すぎる隣国が出たら、周辺と緩い反同盟を作る。
- 保証/警告:小国を守る宣言で、敵の拡張を間接的に牽制。
- 請求の正当性:根拠(コア/請求/宗教・文化)を作ると、開戦コストや講和コストが軽くなる。
C. 研究ロードマップ例(序盤〜中盤)
- 兵站・補給・維持費の軽減(長期戦体力)。
- 生産性と流通(ROIが良くなる=第3回の再現性アップ)。
- 軍の質(士気・戦術・装備)。勝てる戦闘の幅が広がる。
- 統治効率(行政・統制の通り)。税も徴兵も乗数がかかる。
事故らない戦争原則と講和、アフターケア
- 地形と季節:川渡り・山岳・冬将軍は攻め側が不利。勝てる地形を選ぶ。
- 前線密度:細い回廊に詰め込みすぎない。包囲される形を作らない。
- 損耗(Attrition)管理:人数上限を超えたスタックはその場でお金を燃やす。包囲部隊は細く。
- 講和の順序:コア/請求のある州→要衝→借金・賠償。欲張らず反撃されにくい線で締める。
- 占領後のケア:
- 統制の通りを上げる(行政・治安)。
- 食料と収容力を確保(第2回)。
- 反乱の芽は短期(特権・治安)と長期(文化・宗教)で二段処理。
よくあるQ&A(超要約)
- Q:序盤ぜんぜん勝てない → A:士気満タン前に突っ込んでない?地形悪くない?2:1の局地優勢を守ってる?
- Q:戦争が長引く → A:目標を絞って早講和。補給線・要塞・損耗を見直す。
- Q:同盟が集まらない → A:距離・関係値・信頼・共通の敵をチェック。関係改善を先に。
まとめ
- 勝ち筋は準備→短期決戦→早講和、負けない筋は抑止と同盟。研究は“今の詰まり”から解くのが最短。