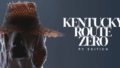ラリーで一番お世話になるパーツって何?って聞かれたら、ブレーキはかなり上位に入るはず。
止まるだけじゃなくて、「どう減速して、どう車を向かせるか」を全部担当してる重要ポジ。
今回は、
- 現実のブレーキの仕組み
- Assetto Corsa Rally のメニューで何を触ってるのか
- 路面別・ステージ別にどう考えていくか
ここをまとめて一気にやる感じでいくね。
1. ブレーキは「止める装置」じゃなくて「速度コントローラー」
まず意識から。
ブレーキって、
- 車を減速させる
- 前後荷重を動かして姿勢を作る
- タイヤのグリップを“どのくらい使うか”を決める
この3つを同時にやる装置。
特にラリーだと、
- コーナー進入で「どのタイミングでどれくらい踏むか」で、
- ちゃんと曲がっていくか
- オーバー/アンダーが出るか
一気に変わる
だからブレーキセッティングは、
- 最大制動力を上げるってより、
- 踏んだ量と車の反応を、自分のイメージに合わせる
ための調整、ってイメージの方がしっくりくる。
2. ブレーキシステムの基本構造をざっくり整理
ゲームのメニューだと英語だらけで分かりにくいから、一回ばらして整理しよ。
2-1. ディスク(Disc)
ホイールの内側でくるくる回ってる円盤。
ここをパッドで挟んで、回転を止めてる。
- 直径 → 大きいほど「テコの原理」で大きなブレーキトルク
- 厚み・通気 → 厚くて中がスリット入ってる(ベンチレーテッド)ほど冷えやすい
ざっくり、
- 大径・通気あり
- よく止まる
- フェードしにくい(長いステージ向き)
- 小径・通気なし
- トルク小さめ
- 軽い
- 低グリップ路面だと、逆に扱いやすいことも
2-2. キャリパー(Caliper)
ディスクを両側から挟んでる“カニばさみ”みたいなやつ。
- 中のピストン面積が大きいほど、同じ油圧でも強く挟める
- ピストン数が多いほど、パッドを均一に押しやすい(効きもコントロールもしやすい方向)
でも、
- ディスクとの組み合わせ
- パッドのコンパウンド
で最終的な効き方はかなり変わる。
だから「このキャリパーはこのディスクとセット前提」みたいな組み合わせが多い。
2-3. パッド(Pad)
ディスクを直接こすってる摩材。
- 柔らかめのパッド
- 初期からガツンと効く
- 摩耗早い
- ロックさせやすい(強く踏みすぎるとすぐタイヤ悲鳴)
- 硬め・耐久寄りパッド
- 最初はマイルド
- 長いステージでもタレにくい
- コントロール幅は広め
ラリーだと、
- 短いSS → 効き重視の柔らかめ寄り
- 長いSS → 耐久寄りで、最後まで踏める方向
みたいな分け方もアリ。
2-4. マスターシリンダー(Master Cylinder)
ペダルを踏んだ力を油圧に変えてるポンプ役。
- ボア径(太さ)が小さい → 高い油圧が出る → 少し踏んでもよく効く
- ボア径が大きい → 低い油圧 → 強く踏まないと効かない(そのかわりロックしにくい)
ゲームのセッティング値では、
- 数値を上げると、ライン圧が下がる方向(効きマイルド)
- 数値を下げると、ライン圧が上がる方向(効き強め)
って解釈になってることが多い。
感覚的には、
「マスター値 ↑」 = ロックしにくい、踏んでもまだ余裕ある感じ
「マスター値 ↓」 = ロックしやすい、軽く踏んで即ガツン系
みたいなイメージでOK。
2-5. Assetto Corsa Rally のメニューと対応ざっくり表
ゲーム内だとだいたいこんな感じで並んでるはず。
- Disc → ディスクのサイズ・タイプ選択
- Caliper → キャリパー(ピストン面積・構造)の選択
- Pad / Shoe → パッドのコンパウンド/特性
- Master Cylinder → ペダル踏力 vs ライン圧の関係(効き方のカーブ)
- Front Bias / Brake Balance → 前後のブレーキ配分
- Handbrake Force → サイド引いたときのリアブレーキの強さ
ここをバラして理解しておくと、後から数字触るのかなりやりやすくなる。
3. ディスク・キャリパー・パッドの選び方
3-1. ディスク:トルクと冷却のバランス
考えるポイントはこの2つ。
- どこまで強い制動力が欲しいか
- ステージ終盤まで熱でタレずに持たせたいか
ラリー的に見ると、
- ターマック高グリップ × 高速セクション多め
- 大きめディスク
- 通気性のいいタイプ(ベンチレーテッド)
- 強めのパッド
- グラベル × ローグリップ × 細かいコーナー多め
- やや小さめディスクでもOK
- 通気はあった方が安心だけど、そこまでシビアじゃない
低グリップ路面であまりに強いブレーキ付けると、
ちょっと踏んだだけでロックしてタイヤが滑りっぱになるから、
あえて「ほどほど」のディスクにするのも全然アリ。
3-2. キャリパー:効きとペダルフィール
キャリパー強めにすると、
- 同じマスターシリンダーでも、少ない踏力で強く挟める
- でも、ピーキーになりやすい
なので、
- ターマックでしっかり止めたい
- コースに高速ブレーキングゾーンが多い
みたいな時は、強めキャリパー+少し大きめマスターで「ガツンと効くけどロックしすぎない」方向にまとめるのが定番。
逆に、
- グラベルでロックさせたくない
- 長いステージで楽に走りたい
なら、キャリパーは一段階マイルド寄りに落として、その代わりペダルをしっかり踏みにいく感じにまとめるのもアリ。
3-3. パッド:効き・耐久・コントロール性
パッド選びに迷ったら、まずここだけ意識すればOK。
- 効き重視パッド
- 初期制動が強い
- タイヤロックしやすい
- 短距離・タイムアタック寄り
- 耐久寄り・マイルドパッド
- 踏み増していくと効きが立ち上がるタイプ
- 長いステージ・低グリップで扱いやすい
Assetto Corsa Rally だと、
「ちょっと踏んだだけでロックする」「ペダルの遊びが無さすぎる」と感じたら、
- いきなりマスターいじる前に、パッドを一段階マイルドにする
っていうのもあり。
4. マスターシリンダーとブレーキバランスの考え方
ここがブレーキセッティングの“心臓部”。
4-1. マスターシリンダー値で何が変わるか
さっき軽く触れたけど整理すると、
- マスター値を上げる
- ライン圧 ↓
- いっぱい踏んでもロックしにくい
- ペダルストローク長め
- コントロール幅広め
- マスター値を下げる
- ライン圧 ↑
- 軽く踏んだだけでよく効く
- ロックしやすい
- ペダルストローク短め
ラリー的には、
- グラベル・ウェット → マスター値は少し高め(ロックしにくい方向)
- ターマック・高グリップ → マスター値は少し低め(軽く踏んでガツンと止める)
みたいな方向性が定番。
ただし「低めにしすぎる」と、
ほんのちょっと触っただけでタイヤがロックして、
ABSない車だとマジで乗れたもんじゃなくなるから、
1ステップずつ試すのが安全。
4-2. Front Bias(ブレーキバイアス)のイメージ
Front Bias は「前後どっちにどれくらい効かせるか」。
- 前寄り(フロントバイアス大きめ)
- ブレーキング時はアンダー寄り
- 安定して止まりやすい
- 初心者・ロングステージ向き
- 後ろ寄り
- ブレーキでリアが回りやすい
- コーナー進入でクルッと向き変わる
- その代わりスピンしやすくて上級者向き
ラリーでは、
- ミスしても生き残りたいなら「やや前寄り」
- 攻めたいステージだけ「ほんの少しだけ後ろ寄り」にして回頭欲を足す
みたいな使い方がやりやすい。
4-3. 「バイアス値=そのままトルク比」じゃない理由
ここちょっと引っかかりポイント。
ゲームのメニュー上で
「Front Bias 60:40」とか見えると、
あ、前60%・後40%で効いてるんだな
って思いがちなんだけど、実際は
- ディスクの直径
- キャリパーのピストン面積
- パッドの摩擦係数
全部ひっくるめた“最終ホイールトルク”の前後比とは
必ずしも一致しない。
だから、
- Front Bias を 1クリック変えたときの挙動は、
実際に走って確かめるしかない
って割り切っちゃった方が早い。
4-4. 調整の基本手順(おすすめ)
ブレーキがしっくりこないときは、こんな順番で触ると迷子になりにくい。
- パッドを決める
- ステージ長と路面に合わせて「効き寄り」か「耐久寄り」か決める
- ディスク/キャリパーで“最大ブレーキ力のレベル”をざっくり決める
- 足りないなら一段強い組み合わせへ
- マスターシリンダーで“ロックしにくさ”を調整
- ロックしすぎ → 値を少し上げる
- 全然止まらない → 値を少し下げる
- Front Bias で“安定寄りか、回頭寄りか”を調整
- スピン多い → 前寄りに
- 進入で曲がらない → ほんの少しだけ後ろ寄り
この順番守るだけでも、ブレーキ沼から結構抜けやすくなる。
5. ハンドブレーキと Handbrake Force
5-1. ハンドブレーキの役割
ラリーでのサイドブレーキは、
- タイトなヘアピン
- 低速のシケイン
で車を回すためのツール。
普通のペダルブレーキで減速して、
最後の一発でサイドを“キュッ”と引いてリアを滑らせて向きを変える、
って使い方がメイン。
5-2. Handbrake Force の考え方
ゲームの Handbrake Force は、
- 値を上げる
- 軽く引いただけでリアがガツンとロック
- よく回るけど、制御シビア
- 値を下げる
- 強く・長く引かないとロックしない
- 回転はマイルドで、コントロールしやすい
グラベルだと、
ちょい強めにしておいて「クイッと引いたらちゃんと回る」ぐらいが気持ちいい。
ターマックで強すぎると、
- 引いた瞬間にリアが完全ロック → スピン
みたいな地獄になるから注意。
5-3. リアブレーキ+Handbrake Forceのセットで考える
リアのディスク&パッドが強すぎると、
- Handbrake Force を低めにしても、
引いた瞬間にすぐロックしたりする。
逆に、
- リアを小さめディスク+マイルドパッドにすると、
Handbrake Force は少し高めでも、
滑り出しがゆっくりでコントロールしやすい。
なので、
- ヘアピン多いステージ → リアを少し強め+Handbrake Force は控えめ
- あまり使わないステージ → リアは普通のまま、Handbrake Force も控えめ
ってざっくりセットで考えるのが分かりやすい。
6. 実戦セッティング例と試し方
6-1. グラベル SS 用のざっくりベース
※数字はイメージなので、実際は自分の車種・デフォルト値からの「方向性」として使う感じで。
- ディスク
- フロント:中〜やや大きめ
- リア:一段小さめでもOK
- パッド
- フロント:効き中くらい〜やや強め
- リア:一段マイルド寄り
- マスターシリンダー
- デフォルトより少し“値大きめ”(ロックしにくい方向)
- Front Bias
- デフォルトより1〜2クリック前寄り
- Handbrake Force
- 中〜やや高め
- ヘアピン多いステージなら、テストしながら少しずつ上げていく
狙いは、
- 普通のブレーキでは安定重視
- どうしても曲げたい時だけハンドブレーキでクイッと回す
ってバランス。
6-2. ターマック SS 用ベース
- ディスク
- フロント:大きめ+通気あり
- リア:中くらい
- パッド
- フロント:効き強め
- リア:効き中〜ややマイルド
- マスターシリンダー
- デフォルトより少し値小さめ(効き強め方向)
- でもロック地獄になるほどは下げない
- Front Bias
- デフォルト付近〜1クリック前寄り
- 後ろ寄りにしすぎると、高速進入で一気にスピンゾーン
- Handbrake Force
- グラベルより控えめ
- 「引いたら確実に回る」じゃなく、「引きすぎたら危ない」くらいの意識で
ターマックは基本、
- ブレーキペダルと荷重移動で曲げる
- サイドは“最終手段”くらいの扱い
にしておくと安定しやすい。
6-3. テスト走行のやり方
ブレーキは「感じ」で語りがちなんだけど、
セッティング試すときはちょっとだけ理系ムーブすると分かりやすい。
- 走るステージを1本決める
- ベースセットで1〜2本走る
- 「どのコーナーでロックするか」「どこで曲がりにくいか」をメモ
- 変更は1箇所だけにする
- 例:マスターシリンダー+1ステップ
- 同じステージを同じペースで走って、変化だけ確認
- OKならそのまま、ダメなら元に戻して別の項目を触る
やりがちなのが、
- 一気にマスターもバイアスもパッドも変えて、何が原因か分からなくなるパターン
なので、1項目ずつ・同じ条件で比較が一番効く。
6-4. セッティングとドライビングの境界線
最後にちょっと大事な話。
- ベストタイムから毎回±2〜3秒くらいブレる
- 同じミスを何回もやらかしてる
こういう状態って、
ブレーキセッティングより自分のドライビングの再現性の方が先だったりする。
- 進入のブレーキポイントを毎回同じにする
- 踏み始め→踏み増し→抜き、のリズムを意識して揃える
ここがある程度揃ってから、
それでも「回りたくないのか」「止まりきれないのか」
を分析して、初めてセッティング変更が効いてくる感じ。
7. まとめ:ブレーキは「効き」じゃなく「扱いやすさ」で見る
今回のポイントをざっくりまとめるとこんな感じ。
- ブレーキは
- 減速
- 荷重移動
- 回頭
を同時にコントロールする装置
- ディスク・キャリパー・パッドで最大制動力と耐久性を決める
- マスターシリンダーでロックしやすさとペダルフィールを整える
- Front Bias で安定寄りか回頭寄りかを微調整
- Handbrake Force は
- グラベル → やや強め
- ターマック → 控えめ
が基本イメージ
- 調整は
- パッド
- ディスク/キャリパー
- マスター
- バイアス
の順番で触ると迷子になりにくい
- 1回の変更で、1項目だけ触って同じステージで比較するのが大事
ブレーキが自分好みになると、
「怖さ」が一気に減ってラリー全体のテンションも上がるから、
ちょっと時間かけてでもここは詰めておきたいところ。
次に走るときは、まず今の車で
・どこでロックするか
・どこで曲がらないか
ここをメモるところから始めてみて。
そこから逆算して、今回の内容に当てはめていけば、かなりいいラインまで持っていけるはず。
セッティング関連記事
- Assetto Corsa Rallyセッティング入門|セッティングを触る前に知っておきたいこと
- Assetto Corsa Rally 足回りセッティング超入門 第1回 サスペンション
- Assetto Corsa Rally 足回りセッティング超入門 第2回 ダンパー
- Assetto Corsa Rally 足回りセッティング超入門 第3回 アンチロールバー
- Assetto Corsa Rally 駆動系セッティング超入門 第4回 駆動系って何してるの?
- Assetto Corsa Rally 駆動系セッティング超入門 第5回 LSD
- Assetto Corsa Rally 駆動系セッティング超入門 第6回 ギアボックス
- Assetto Corsa Rally セッティング超入門 第7回 タイヤ
- Assetto Corsa Rally セッティング超入門 第8回 ブレーキ
- Assetto Corsa Rally セッティング超入門 第9回 電子制御