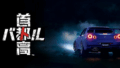冷戦ど真ん中の海空戦を、ミサイルとセンサーの駆け引きでガチ体験できる海戦シムが『Sea Power』。一時停止しながら艦隊と航空隊を緻密に動かすタイプで、レーダー/ESM/ソナーの運用が勝敗を左右。学習コストはあるけど、その分“わかった瞬間”が超気持ちいいやつ。あたしが要点まとめるね。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ゲームタイトル | Sea Power: Naval Combat in the Missile Age |
| デベロッパー | Triassic Games AB |
| パブリッシャー | MicroProse Software |
| ジャンル | 海戦シミュレーション / リアルタイム(ポーズ可) |
| 発売日 | 早期アクセス開始:2024年11月12日(継続中) |
| 対応言語 | 英語、ドイツ語、ロシア語、簡体字中国語 / 日本語:なし |
| 価格(定価) | ¥5,500前後 |
どんなゲーム?
冷戦期(だいたい60〜80年代)の北大西洋、ペルシャ湾、トンキン湾、地中海などを舞台に、NATOとワルシャワ条約機構の海空戦を描く“ポーズ可のリアルタイム”海戦シム。艦隊の編成と航空戦力の運用、そして探知→識別→交戦をめぐる情報戦がゲームのコアだよ。
- 指揮スケール:タスクフォースや護衛群、哨戒機・空中早期警戒機・対潜ヘリなどをまとめて管制。150種以上の艦艇、60種以上の航空機、130種規模の兵器システムが登場。
- センサー戦の駆け引き:レーダーやアクティブ・ソナーは強いけど“光ったら見つかる”。まずは受動探知(ESM/パッシブ・ソナー)で相手の位置と意図を読むのが鉄板。電波発信はここぞで使う。
- 交戦規則とドクトリン:識別未完のターゲットは撃てないし、誤射のリスクもある。ROEの切り替え、発射間隔、同時攻撃のタイミング調整が腕の見せどころ。
- 環境要素:時間帯や天候、海況で探知性能が変わる。夜間低空アプローチや温度躍層を利用した対潜など、地味だけど効くテクが気持ちよく刺さる。
- 作って遊べる:シナリオエディタとSteamワークショップ対応。既存シナリオで基本を押さえたら、人気作例や自作で無限に練習できる。
コミュニティの反応は?
- 良いところ:
- “センサー運用が勝敗を決める”冷戦らしさが唯一無二。射程外からの先制、欺瞞、同時飽和攻撃の設計が楽しい。
- シナリオの厚さとエディタ/Workshopで長く遊べる土台。アップデートのたびに改良・作例が増えてる。
- Steamの評価は「非常に好評」寄りで推移。コア層の満足度が高い。
- 気になる点:
- 学習コストは高め。ASW(対潜)とEW(電子戦)を理解するまで少し壁がある。
- ダイナミック・キャンペーンは鋭意開発中。ロードマップの動きは追ってチェック。
オススメや期待ポイント
- “まず見つけ、見つからない”が勝ち筋:発信系センサーの常時ONは禁物。受動探知で敵情を掴み、要所だけアクティブで刺す運用に慣れよう。
- 哨戒とヘリで“前衛の目”を作る:遠距離の目印は航空。対空網や対潜網と連携して、無駄に艦を前に出さないのが安全で強い。
- 小規模シナリオから入門:最初は艦数が少ない作戦で、探知→識別→交戦の一連を体で覚えるのが近道。キー操作より判断の順番を優先して練習。
- 将来の伸びしろ:エディタでコミュニティ発の名シナリオが増加中。ダイナミック・キャンペーンが実装されたら、劇的に遊び方が広がるはず。
まとめ
“撃ち合い”より“見合い”が主役。情報優勢を積み上げて、一撃で決める。この手の現代海戦シムが好きなら、早期アクセスの今から触って損はないと思う。あたし的には、センサーとROEの理解が進むほどプレイが面白くなるタイプだよ。